日本銀行(にほんぎんこう)
Bank of Japan(バンク・オブ・ジャパン)
日本銀行の機能(発券銀行、銀行の銀行、政府の銀行)
発券銀行…日本銀行券の発行を行う
銀行の銀行…民間銀行の預金を預かり、預金・貸付の取引や債券・手形の売買を行う
政府の銀行…政府の預金を預かり、国庫金事務、国債事務、外国為替事務を行う
日本銀行は、1882(明治15)年に、日本銀行条例(日本銀行の役割・業務・組織などを定めた)に基づいて創設された日本の中央銀行です。略して日銀と呼ばれています。
日本銀行には、(1)発券銀行、(2)銀行の銀行、(3)政府の銀行 という3つの機能があります。
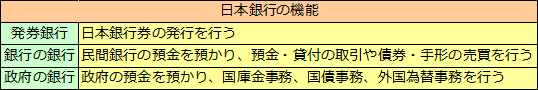
≪発券銀行≫
日本銀行は、紙幣を発行できる唯一の銀行です。発券銀行の業務として、(1)日本銀行券の発行、(2)汚れ・傷みのひどい紙幣の回収、(3)紙幣の真偽のチェック などを行っています。
日本銀行券(1万円、5千円、2千円、千円)は、独立行政法人「国立印刷局」が印刷し、日本銀行が発行しています。硬貨は、独立行政法人「造幣局」が鋳造し、補助貨幣として政府が発行しています。いずれも受払いは、日本銀行の窓口を通して行われます。
※2003(平成15)年4月から、財務省印刷局(旧 大蔵省印刷局)は独立行政法人「国立印刷局」に、財務省造幣局(旧 大蔵省造幣局)は独立行政法人「造幣局」になりました。
≪銀行の銀行≫
日本銀行は、民間銀行の預金(当座預金)を預かり、預金・貸付の取引や債券・手形の売買などを行っています。このように、民間銀行が日本銀行に「預け金口座」を持っていることから、日本銀行は「銀行の銀行」と呼ばれています。
一方、企業や個人は、民間銀行に「預金口座」を持っています。企業や個人が、日本銀行に預金口座を持つことはできません。発行された現金通貨は、日本銀行から民間銀行に流れ、そして民間銀行から個人や企業に供給されています。
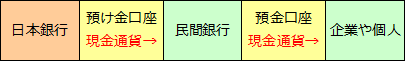
※日本銀行に当座預金を置いている金融機関には、銀行、信用金庫、証券会社、証券取引所、証券金融会社、短資会社、預金保険機構などがあります。
≪政府の銀行≫
日本銀行は、政府の預金(当座預金)を預かり、国庫金の出納事務(税金、社会保険料、公共事業費などの政府の歳入・歳出に伴う受払い)、国債に関する事務(発行・流通・償還など)、外国為替に関する事務(外国為替平衡操作のための為替介入)を行っています。そのため、「政府の銀行」と呼ばれています。
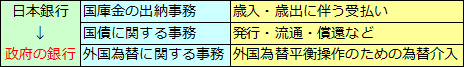
金融大学TOP > よくわかる!金融用語辞典 > 日本銀行の機能(発券銀行、銀行の銀行、政府の銀行)
